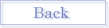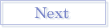中間考査 《2》
土曜日は、午前中は授業、午後は部活だった。
夕方、部活が終わった後で、手塚は不二の家を訪れた。
過去何度か来た事があって、初めてというわけではないが、
「失礼します」
と入ってみると、家人が誰もいなかったので、手塚はいぶかしんだ。
「あ、今日は誰もいないんだよ、うち」
不二が笑いながら言った。
「誰もいないのに、お邪魔してもいいのか?」
「全然構わないよ、うち、そういうの気にしないから」
そう言ってさっさと上がっていく不二の後について、手塚は迷いつつ、脱いだ靴をきちんと揃えて上がった。
「君って、そういうトコ、本当に几帳面だよね」
不二が振り返って言う。
面白がっているような言い方に、手塚は少々むっとした。
「ごめんごめん、じゃあ、僕の部屋へ来て」
手塚の機嫌を損ねたのが分かったのか、不二がとりなすように言ってきた。
つまらないことでむっとしたのを気付かれて、手塚は赤面した。
どうも、不二と話していると自分のペースが狂う。
いつも他人に見せている『手塚国光』としての姿とは違う、素の自分を見られてしまっているような気がする。
-------「手塚、可愛いね」
最近、よく不二から言われる言葉を思い出して、手塚は落ち着き無く視線を揺らめかした。
自分に向かって可愛いなどと言ってくる人間は誰もいない。
昔は言っていた両親でさえ、今は自分を大人として扱ってくれている。
……一体、自分のどこをみて可愛いなどと思うのか。
『手塚は頼りになるよなあ』
『手塚君がいると、安心だわ』
先生方にはこう言われるし、同級生や後輩からも常に一目置かれている。
そんな自分に対して、不二はどうして。
『……色っぽいよ……』
この間言われた言葉も思い出してしまって、手塚は不二の部屋へ上がる階段を登りながら、頬を赤らめた。
どうも、変だ。
なぜ心臓がどきどきするのだろう。
「僕の部屋に入るの初めてだよね。結構綺麗でしょう?」
二階の東の部屋が不二の部屋だった。
案内されて、中を見ると、シンプルでこざっぱりとした部屋だった。
壁際に机とオーディオラック、反対側の壁に沿ってベッドが置かれている。
窓際には本棚とテレビ、それに観葉植物がセンス良く飾られていた。
気取っていないが、どことなく上品な部屋だった。
釣り具や山の写真が主の自分の部屋とは、雰囲気が違う。
「あ、ここに座って。……飲み物とか持ってくるから」
そう言って不二が出ていくのを、手塚はカーペットの上に座ったまま見つめた。
オーディオラックには、CDではなくレコードが並べられていた。
ラックの上には、アンティークなオーディオ器具が乗っている。
不二の趣味だろうか。
自分の知らない不二の一面を見たような気がして、手塚は戸惑った。
「はい、手塚はこれでいい?」
不二が、手にトレイを持って部屋に入って来た。
トレイの上には、ミネラルウォーターと緑茶のペットボトルがあった。
「あ、すまない………」
なんとなく気恥ずかしくなって口ごもりながら言うと、不二がくすっと笑った。
「いいって、勉強教えてもらうんだからね。……じゃあ、お願いするかな」
不二がそう言って、バッグから教科書類を取り出すのを、手塚はぼんやり眺めた。
なんとなく、勝手が違う。
普段なら、自分がしっかりしていなければという気持ちで、何をするにも率先して模範を示すのが、手塚の行動パターンである。
それが、不二の前だと、どうもうまく行かないのだ。
「竜崎先生に脅されちゃってね。今度のテストで点数が下がったら容赦しないよって」
ノートを広げながら、不二が言う。
「テニスの方が良ければ、成績は少しぐらいおまけしてくれたっていいのにねえ」
ね、手塚?と声をかけられて、手塚は自分がしばし呆けていたのに気が付いた。
「あ、ああ………いや、それは駄目だな。テニスはテニス、勉強は勉強だ」
「あはは、手塚ならそう言うと思ったよ」
不二が目を細めて笑う。
不二に笑いかけられて、手塚は視線を逸らして咳払いをした。その日は部活が終わってから不二の家に来たので、来た時点で既に夕方だった。
だから、手塚は遅くならないうちに帰るつもりだった。
夕食をご馳走になってしまったりしてはいけない。
家人がいなければ尚更のこと、早々に退出しようと思っていたのだが、手塚がその事を言い出すと、不二が、静かに、しかし頑とした様子で、夕飯を食べて行けと言ってきた。
「今日は僕しかいないから、独りで食べてもつまらないんだ。だからお願いだよ」
言葉は穏やかながら、じっと自分を見据えて言ってくる不二には、手塚は弱い。
どうにも断りきれなくなってしまうのだ。
「………じゃあ、済まないが、ご馳走になるか」
そう答えると、不二が破顔した。
「良かった、じゃあ、夕飯作るから、ちょっとテレビでも見ててね」
「俺も手伝おう」
「あ、大丈夫、作るっていっっても、レトルトを暖めるだけだよ。食べていってなんて言った割に、何もなくて悪いね」
「……いや………」
素っ気ない不二の答えに、何か手の込んだ料理でも作るのかと思って構えた手塚は拍子抜けしてしまった。
手塚自身は、自宅で料理の手伝いをすることが多い。
時間のある休日などには、カレーぐらいなら自分で作ったりもする。
小さな頃から、身の回りのことはなんでも自分で出来るようにとの両親の教育の成果だったが、それでなくても、手塚はなんでも自分でやっていた。
それが当然だと思っていたし、そういう事が出来る事を期待されているとも思っていた。
…………不二はどうなのだろうか?
ふと疑問が湧いて、手塚は不二の部屋を見回した。
片づけはしているのだろうが、自分ほどきちんとしているわけではない。
それでいて、不思議に居心地のいい部屋だった。
いつも自然体で、気負わない不二の性格がよく出ている部屋だった。
自分とは、違う。
不意にそういう思いが湧いて、手塚は唇を噛んだ。
「はい、できたよ」
程なくして、不二が、部屋まで大きなトレイを運んできた。
トレイには、銀色のアルミ箔の皿に入ったグラタンが湯気を立てていた。
その他、即席で作ったらしい野菜サラダとスープが乗っている。
「冷凍になってたやつを温めただけだけど、まぁ、いいよね?」
「ああ、悪いな」
「……ま、君みたいにちゃんとした料理作れなくて悪いけどね」
不二が含み笑いをする。
「本当はいろいろ作れるんだろう?」
不二の言っていることが信用できなくて、グラタンを頬張りながら尋ねると、不二が肩を竦めた。
「本気でやればね。でもさ、人間、難しいのは本気を出すって事だろう、手塚? やればできるけど、やれない人間がたくさんいるからね」
「……まぁ、そうだな……」
「あははっ、手塚、眼鏡が曇ってるよ?」
グラタンの湯気で眼鏡が一瞬白くなったのをめざとく捉えて、不二が笑った。
不二はいつも笑っているような目をしているが、実際に笑うと表情全体が柔らかくなる。
笑ったような目をしていても、心の中では冷静に作戦を練っている彼を知っているだけに、手塚は表情を崩して笑う不二を見て、なんとなく嬉しくなった。
不二がこんな表情をするのは、自分の前だけだ。
なぜかそんな気がしたのだ。
(バカだな…………)
自分がくだらない事を考えているのに気付いて、手塚は恥ずかしくなった。
不二が自分にだけ優しいなどと思い込んでいるような気がしたのだ。
人当たりの良い不二のこと、誰にでもにこやかに応対するんだろう。
別に、自分にだけじゃない。
そう考えて、ふと残念な気がして、手塚は内心狼狽えた。
(一体、何を考えているんだ!)
自問自答して、くだらない考えを頭から追い払おうとする。
「ねえ、ここはどういう風に解けばいいのかな?」
夕食が終わって、不二が数学の問題を聞いてくる。
「あ、ああ………そこは………」
どうにも自分のペースに戻れなくて、手塚はことさら平静を装って、問題を考える振りをした。